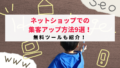ネットショップを始めたいけれど、「在庫管理って難しそう」「家に大量の商品を置くのはちょっと…」と不安を感じていませんか?
副業として物販を考えている人にとって、在庫管理の手間やスペースの確保は大きなハードルです。
とはいえ、エクセルだけで管理するには限界があり、放っておくと在庫のズレや機会損失にもつながりかねません。
この記事では、スキルに自信がなくても扱いやすい在庫管理のコツを解説しつつ、副業・省スペース志向の人におすすめのクラウド型在庫管理システム5選を比較紹介します。

ネットショップ運営を効率化したい方は、ぜひ最後までチェックしてみてください。
ネットショップで在庫管理が必要な理由

ネットショップ運営において、在庫管理は単なる作業ではなく、ビジネス成長の土台です。
まず1つ目は「販売機会の最大化」。
在庫切れは売上損失だけでなく顧客の離脱にも直結します。
2つ目は「キャッシュフローの健全化」。
過剰在庫は資金を圧迫し、仕入れの柔軟性を奪います。
3つ目は「顧客満足度の維持」。
商品がすぐ届くかどうかは、評価やリピート率に大きく影響します。
4つ目は「データ活用による戦略強化」。
在庫情報を分析すれば、売れ筋の傾向が見え、無駄な仕入れを防げます。
クラウド型ツールを活用すれば、初心者でも手軽に精度の高い管理が可能になります。
在庫切れによる販売機会の損失を防止できる
在庫切れは、単なる「商品がない」だけの問題ではありません。

たとえば、SNSで話題になった商品を購入しようとアクセスした顧客が「在庫切れ」の表示を見て離脱した場合、もう二度と戻ってこない可能性があります。
特に、リピーターの多い美容系やガジェット系では、「安定して買える店」であることが重要です。
さらに、最近は「即日発送」や「在庫あり表示」がECプラットフォームのアルゴリズム評価にも影響を与えると言われており、在庫切れが続くと検索順位が下がるケースもあります。
クラウド在庫管理システムを使えば、売れ筋商品がリアルタイムで把握でき、在庫が少なくなったタイミングで自動アラートを出せる機能もあります。
また、「在庫連携機能」により、BASEやShopifyなど複数の販売チャネル間で在庫数を自動で同期できるため、ヒューマンエラーのリスクも軽減されます。
販売機会を逃さないためには、予測・アラート・連携といった「仕組み」が欠かせません。
小さく始めるネットショップでも、売上を安定させるためには、在庫管理こそが最も重要な業務のひとつです。
過剰在庫による資金繰り悪化を回避できる
在庫が多すぎると、思わぬ形で経営を圧迫します。
まず、仕入れた商品が売れなければ、それだけ資金が「モノ」に変わって寝てしまい、新たな仕入れや広告費などに使えなくなります。
これが「キャッシュフローの悪化」です。
副業で運営している場合でも、余剰在庫が積み重なれば、想定以上の資金が拘束され、次のアクションが打てなくなります。
また、自宅保管の場合、物理的なスペースも取られ、生活空間を圧迫するだけでなく、湿気や日焼けによる品質劣化のリスクも無視できません。
特にアパレルや食品系は、保管環境によって商品価値が下がることがあります。
こうしたリスクは、在庫管理ツールを使って「売れ行きに応じた仕入れ量」を見える化すれば回避可能です。
最新のシステムでは、過去の売上データや季節変動から自動で発注量を提案してくれるAI機能も登場しています。
無駄な在庫を減らし、キャッシュフローを保つには「売れる分だけを、売れるタイミングで仕入れる」ことが鉄則です。
顧客満足度と店舗評価の向上につながる
適切な在庫管理は、顧客満足度の向上に直結します。
理由はシンプルで、「注文した商品が予定通り届く」という基本的な期待に応えることが、信頼と評価を生むからです。
とくにネット通販では顔が見えない分、配送の正確さや速さが店舗の信用度になります。
在庫が正確に把握されていれば、誤発送や発送遅延も減り、結果としてレビュー評価やリピート購入率の向上につながります。

最近では、レビューに「発送対応が早かった」「在庫があって助かった」といった内容が記載されることで、他の新規顧客にも安心感を与え、購買意欲を高める効果も!!
顧客体験を向上させるためにも、地道な在庫管理は欠かせない業務のひとつです。
売れ筋商品の傾向分析が可能になる
在庫データは、単なる「残り個数の記録」ではなく、販売戦略のヒントが詰まった貴重な資産です。
どの商品が、いつ・どのくらい売れたかを分析することで、季節性やトレンドの動きを把握できます。
たとえば、「週末に売れやすい商品」「月初に需要が高まるアイテム」などが分かれば、仕入れやプロモーションのタイミングも調整できます。
最新の在庫管理ツールでは、売上と在庫のデータを自動で可視化し、商品ごとの販売ペースや在庫回転率をグラフで確認することも可能。
売れ筋の見極めが早ければ、人気商品への集中投資や在庫最適化によって、利益率の向上も期待できます。
感覚ではなく、データに基づく運営が成功のカギです。
ネットショップの在庫管理方法3選

ネットショップの在庫管理には、主に3つの方法があります。
それぞれコストや手間、精度に違いがあるため、自分のスタイルや成長フェーズに合わせて選ぶことが大切です。
1.エクセルなどを使った手動管理
2.在庫管理専用のクラウドシステムを使う方法
3.外部倉庫やドロップシッピングを活用する方法
以下では、それぞれの特徴や向いている人、使い方のコツを詳しく解説します。
エクセルを使った手動管理の方法とポイント
副業でネットショップを始める人にとって、一番手軽な在庫管理方法が「エクセル(スプレッドシート)を使った管理」です。
無料で始められ、ある程度のカスタマイズも可能なのが魅力です。
・商品名・SKU(商品番号)
・在庫数
・発注日・仕入れ価格
・販売数・在庫残数
・発送状況
これらを表で管理し、週に1回でも在庫を手入力で更新することで、ある程度の在庫管理は可能になります。
ただし、注意点もあります。
・リアルタイムでの反映が難しい:複数チャネル(例:BASEとメルカリなど)で販売していると、在庫数のズレが起こりやすくなります。
・人的ミスが出やすい:手動入力はうっかりミスや計算間違いのリスクがあります。
・売上や傾向の分析がしづらい:シンプルな表では売れ筋や回転率の把握が難しいため、必要に応じて関数やグラフを使うスキルが求められます。
Googleスプレッドシートを使えばスマホからも編集できるため、外出先でもある程度の管理は可能です。
専用在庫管理システムを使う方法
本格的に在庫を管理したい、あるいは複数の販売チャネルを使っているなら、専用のクラウド在庫管理システムの導入が非常に効果的です。
最近は小規模事業者でも使いやすいシステムが増えており、副業レベルでも十分活用できます。
外部倉庫サービスやドロップシッピングの活用法
在庫を自宅で管理したくない、副業なので時間もスペースもないという方におすすめなのが、「外部倉庫」や「ドロップシッピング」の活用です。
① 外部倉庫(フルフィルメントサービス)
Amazon FBAやロジモプロなどの外部倉庫に商品を預けておけば、受注→梱包→発送まで自動でやってくれます。
冷蔵・冷凍・大型商品に対応したサービスも増えてきています。
② ドロップシッピング
商品の在庫を持たず、注文が入ってから仕入先が直接お客様に発送する仕組み。
BASEやSTORESでも対応できるサービスがあります。
ドロップシッピングを始めるなら、国内の信頼できるサプライヤーから選ぶのが安心です。
代表的な在庫管理システム5選
在庫管理ツールって、種類が多すぎて選ぶだけで一日終わりそう…。
そんなあなたのために、タイプ別でおすすめのシステムをご紹介します!
👶「副業初心者。なるべく簡単に、サポート付きがいい」 → タテンポガイド
👨💼「倉庫を活用して、物流もガッツリ自動化したい」 → ロジザードZERO
🏪「複数モールを活用して運営しながら、成長していきたい」 → ネクストエンジン
📦「とにかく安く、でも多店舗管理したい」 → CROSS MALL
💻「シンプル操作!エクセル感覚で使いたい」 → zaiko Robot
タテンポガイド:複雑なネットショップ業務を、クラウドでシンプルに管理

タテンポガイドは、ECモールや自社サイトを横断して受注・在庫・商品・配送など全業務を一画面で管理できるクラウドサービスです。
ITに詳しくない方でも使えるように、専任スタッフによる導入支援や運用相談が充実しており、初心者にも安心です。
初期費用:無料
月額費用:11,000円(税込)〜 (受注件数、商品点数、店舗数に応じて段階課金あり)
機能制限:商品数10,000点/店舗数5つ/受注件数1,000件までは対応範囲(超過時は追加料金)
拡張性:EC仕様変更や新モールへの対応はシステム側でアップデートされるため安心
初心者向け機能:商品一括登録/在庫・売上レポート/受注処理自動化/サポート対応など
小〜中規模のネットショップで、業務を効率化したい方に最適な一元管理ツールです。
ロジザードZERO:物流管理に強い高機能システム

ロジザードZEROは、WMS(倉庫管理システム)として在庫管理の物流連携に強みを持つクラウド型システムです。
大規模倉庫や3PLを活用するショップに適しています。
物流特化機能:入出荷ロジック、ピッキング管理、在庫ロケーション制御など、業務精度向上のための細かな
設定に対応。
倉庫連携:Amazon FBAやロジクラ、イーロジット等とのAPI連携により、外部倉庫との連動がスムーズ。
大規模事業者向け:長期実績(20年以上)、多数の業務プロセスに対応可能で信頼性高い。
高SKU数や高出荷量の運用に適しています。
コスト構造:導入費用・月額費用は要問合ですが、物流量に応じたプラン設計が可能。詳細は問い合わせベー
スです。
複数倉庫や物流アウトソースを視野に入れている事業者に最適な高度物流管理ツールです。
ネクストエンジン:多店舗連携に強い総合型システム

ネクストエンジンは、Hamee社(NE株式会社)が提供する複数のECモールを横断して在庫・受注・商品情報を統一管理できるシステムです。
業界シェア1位を誇り、導入実績も豊富です。
主要機能:受注管理/在庫同期/商品情報一括登録・更新/アプリ連携による機能拡張
料金体系:初期費用0円、月額3,000円(税抜)〜の基本料+受注件数に応じた従量課金制。
店舗数・商品数の増加による追加費用なし。
強み:楽天、Amazon、Yahoo!、SHOPIFY、BASEなど豊富なモールとAPI連携し、在庫ズレや二重出荷を防
止。
導入事例:17店舗を3人で運営する事例など、小規模体制でも多店舗運営できる柔軟性があります。
複数モールを活用して運営しながら、成長していきたいショップにおすすめです。
CROSS MALL:モール横断管理に特化したツール

CROSS MALLは、複数のECモールや自社ECを一括で受注・商品・在庫管理できるASP型クラウドツールです。
2015年以降小規模〜中規模ショップでも導入しやすさが魅力。
対応モール一覧:楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazon、au PAYマーケット、Qoo10、SHOPLIST、
ZOZOTOWNなど多岐に渡る。
在庫連携の仕組み:各ECサイトでの在庫変動を自動で同期し、売れ越しや欠品リスクを低減。
価格プラン:初期費用0円、月額10,000円(税込)〜、店舗&商品数に応じた定額制で安心。
導入難易度:専任担当者による導入支援あり。
初期設定から運用開始まで手厚くサポートされるので、初心者にも導入しやすい設計です。
在庫数の管理とコストの見通しを重視したい方におすすめです。
zaiko Robot:中小規模ショップ向け簡易システム

zaiko Robotは、中小規模ショップでも導入しやすいシンプルで使いやすい在庫連動システムです。
主に楽天市場など多店舗運営者に人気です。
機能概要:24時間自動で在庫数を各ECモールに同期。売れ逃しや二重出荷を防止します。
セット商品や福袋対応も可能。
低価格導入メリット:基本機能は無料プランもあるほか、有料プランでも比較的価格は抑えめ。
スモールスタートに最適。
操作性の特徴:直感的なUIでPC操作に自信がない方でも扱いやすく、最小限の設定だけで
使い始められます。
活用事例:楽天スーパーセールやキャンペーン時の在庫管理でミス削減、作業負担軽減に成功した店舗多数。
シンプルでコストを抑えつつ、確実に在庫を管理したい方におすすめです。
在庫管理システムの選び方ポイント
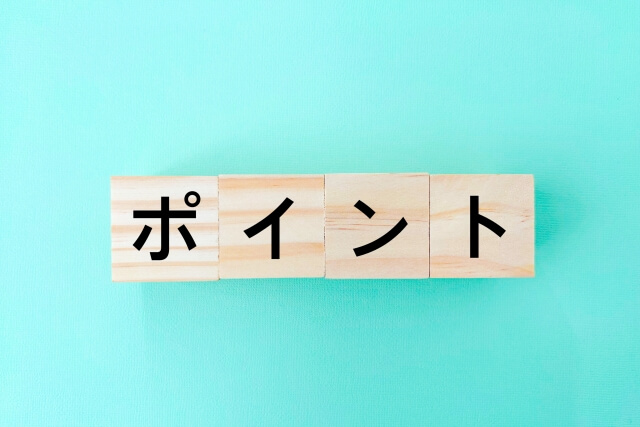
在庫管理システムの選定は、ネットショップ運営の成否を左右する重要なステップです。
導入時には次の5つの視点を意識しましょう。
1.対応モール数・チャネル連携:BASEや楽天、Amazonなど自分が使う販売先とスムーズに連携できるか
2.操作のわかりやすさと導入サポート:初心者でも扱えるUIやマニュアル、導入支援があるか
3.拡張性とカスタマイズ性:ショップが成長しても柔軟に対応できる設計か
4.価格構成(初期費用/月額/追加料金):基本料だけでなく、受注件数や商品数での変動もチェック
5.セキュリティとバックアップ体制:データが安全に守られているか、障害時の復元策があるか
料金体系は初期費用と月額費用に加え、データ容量や利用機能による追加コストの有無もチェックしておくと安心です。
また、セキュリティやサポート体制、万一のトラブル時に頼れる体制が整っているかも見逃せないポイントです。
ショップ規模と商品数に合わせた選択方法
在庫管理システムは、ショップの規模や取扱商品数に応じて最適な選択肢が異なります。
商品数が数十〜数百点、受注件数が月数十件くらいなら、シンプルで低コストなツール(例:zaiko Robotやタテンポガイドの小プラン)で十分。
操作も直感的で、エクセル以上の効率を実感できます。
商品数が数百〜千点、楽天やAmazon、BASEなど複数チャネルで販売している場合、複数モールと連携できる総合型ツール(ネクストエンジンやCROSS MALL)がベスト。
リアルタイム在庫連携と売れ筋分析機能が成長を支えます。
商品数千点以上、物流アウトソースや自社倉庫を使う発注体制なら、ロジザードZEROなど物流特化システムが威力を発揮。
ピッキング管理や複数倉庫対応機能で効率化を図れます。
事業の成長に伴い、在庫管理の要件は変化します。
将来像を見据えた柔軟な選定が鍵となります。
複数販売チャネル連携は必須?確認すべき互換性
最近のネットショップは、自社EC(Shopify/BASEなど)とモール(Amazon/楽天など)を併用するケースが増えています。
この場合、在庫管理ツールが両者にリアルタイム連携できるかどうかが重要です。
具体的には、各モールの注文情報を自動取得し、自社EC側の在庫数と同期するAPI連携が必要です。
API連携の仕組みでは、注文が入ると即時に在庫数が反映され、二重出荷や欠品を防ぎます。
同期頻度は秒単位・数分単位のリアルタイム型から、1時間毎・日次バッチ型まで選べるものもあり、販売のスピードや数量によって選び分けが可能です。
また、CSVインポート・エクスポートだけで競合チャネルと手動で連携するタイプは、少人数・初期運用なら使えますが、売上が増えたタイミングでキャパ越えになります。
将来的にモール拡大や自社ECとの連携を視野に入れるなら、API連携実績のあるツールを選ぶことで安心です。
初期費用と月額コストのバランスを見極める
在庫システムを選ぶ際は、価格構造をじっくり見比べることが大切です。
無料に見えても、受注件数や商品数で追加費用がかかることもあるので、気をつけましょう。
| 項目 | 例1:低コスト型 | 例2:中規模対応型 | 例3:物流特化型 |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 0円 | 0円〜数万円 | 要問合せ(設置支援費あり) |
| 月額費用 | 月5,000円〜 | 月10,000円〜 | 月数万円〜(案件別) |
| 追加コスト | 受注超過で追加料金 | 商品数増で数千円UP | 倉庫連携・APIで変動 |
| ROI(年間換算) | 約10〜20% | 約15〜30% | 約20〜40% |
ROI(投資利益率)は、労働時間削減や欠品減少、広告費削減と合わせて考えると、月額費用の10倍近い効果が見込めることも珍しくありません 。
小規模店舗でも、時間対効果だけで導入を正当化できるケースがあります。
サポート体制とセキュリティ対策の重要性
在庫管理システムを導入した後のサポート体制は、安心して運用を続けるために欠かせません。
トラブルが発生した際に迅速かつ的確な対応が受けられるかどうかは、業務の滞りを防ぐポイントです。
具体的には、電話やチャット、メールでのサポートの有無や対応時間、対応品質を事前に確認しましょう。
また、システム操作でつまずいた場合のマニュアルや動画チュートリアルが充実しているかも重要です。
データセキュリティとバックアップ体制の確認も必須です。
クラウド型の場合、通信の暗号化や多重認証、サーバーの安全管理が行われているか、さらに定期的な自動バックアップ機能が備わっているかをチェックしてください。
万が一のシステム障害や誤操作時でもデータ復旧が可能であれば、事業継続リスクを大幅に減らせます。
・導入サポート体制:チャット・電話・オンライン研修など、使い方を丁寧に教えてくれる体制があるか。
・トラブル対応:障害やデータ破損が発生した場合、サポートは何時間以内に回答してくれるか。
・データセキュリティ:クラウド上の在庫情報は重要情報のため、SSL暗号化・アクセス制限・バックアップの頻度をチェック。
・バックアップ体制:万が一のシステム障害時に、過去データの復元が可能かどうか。
特にクラウド型サービスでは、プロバイダー依存になるリスクもありますが、逆に自社で
サーバー管理しなくて良い利点もあります 。
信頼度の高い事業者かどうか、契約前に確認することで、将来のトラブルを避けられます。
効率的な在庫管理で実現できるビジネス成長とは
適切な在庫管理は、売上向上、コスト削減、そして顧客満足度の向上という三つの柱でビジネス成長を支えます。
例えば、在庫切れによる販売機会損失を防ぐことで、売上が平均10〜15%増加した事例も報告されています。
また、過剰在庫を削減できれば、倉庫費用や陳腐化による損失が年間で20〜30%減少したケースもあります。
さらに、正確でスムーズな受注・発送体制は、顧客の注文ミスや配送遅延を減らし、レビュー評価やリピート率の向上に寄与。
あるECショップでは、在庫管理システム導入後にリピート購入率が約25%改善したという成功例もあります。
売上向上:在庫切れ防止により機会損失が減少し、リピーター率が向上。
コスト削減:余剰在庫削減でキャリーコスト(管理・保管コスト)を10〜30%削減できることも
顧客満足向上:正確な在庫情報と迅速な配送でレビュー評価が上がり、信頼が積み上がる。
今日から始められる在庫管理改善ステップ
今すぐできる在庫管理改善アクションと目標設定の流れです。
・即日実践: 現在の在庫数と受注数をエクセルに記録し、月ごとの回転率を簡単グラフ化。
・短期(1〜3ヶ月): 関数やグラフで売れ筋商品を可視化し、次回仕入れ量を調整。
・中期(6ヶ月): 在庫アラート機能付きツール(例:無料引きで使えるzaiko Robot)を導入し、欠品や過
剰在庫を自動監視。
・長期(1年): AI予測や最適発注機能を備えたシステムへ移行し、仕入れや販促をさらに自動化。
このサイクルを繰り返すことで、小さくても確かな改善が積み上がり、収益改善と業務効率化につながります。
まずはエクセルでもOK、次にシステム、将来は成長に応じて最適化を重ねましょう。
よくある質問
在庫管理の4原則とは?

在庫管理の基本原則は「適正在庫」「先入先出(FIFO)」「回転率重視」「定期監査」です。
これらを押さえることで、在庫ズレやロスを最小化できます。
まとめ
在庫管理は、ネットショップ運営の肝となる重要な業務です。
適切なシステムの選び方やコストバランスを理解し、ショップ規模に合わせた運用を心がければ、売上アップ・コスト削減・顧客満足向上が期待できます。
エクセルから始めて、必要に応じてクラウドツールを取り入れるステップを踏めば、無理なく運営体制を整えられます。
まずは小さく動いて、着実に成長させるための準備を始めましょう。